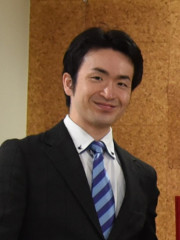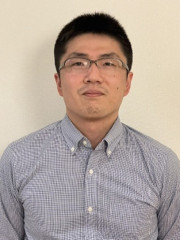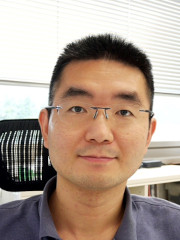各種募集
新化学技術研究奨励賞
新化学技術研究奨励賞ステップアップ賞
公益社団法人新化学技術推進協会(JACI)では、産学官交流連携活動の一環として、新化学技術研究奨励賞を設けています。本奨励賞は、化学産業界が必要とする研究課題を設定し、その実現に貢献することができる若手研究者の独創的な萌芽的研究テーマを発掘・奨励する目的で毎年公募しています。
今年も、下記の通り、環境分野、エネルギー・資源分野、電子情報分野、ライフサイエンス分野、先端化学・材料分野からの12課題と特別課題(革新的計測分析分野)を設けましたので、奮ってご応募下さい。
また、研究奨励賞受賞者を対象にしたステップアップ賞を設けていますので、将来の応募も念頭に入れていただき、本研究奨励賞にご応募ください。
| 第12回新化学技術研究奨励賞課題一覧 | |
| 特別課題 | 革新的化学工学に関する基盤的研究 |
|---|---|
| 課題1 | グリーンイノベーションを推進するための資源・プロセス・評価技術等に関する環境技術の研究 |
| 課題2 | 新しい資源代替材料・技術の創製、および資源の節約・回収・再利用に関する基盤的研究 |
| 課題3 | バイオマス由来製品の事業化課題を解決する革新的な機能を有する素材の開発研究、又は革新的なバイオマス変換技術の研究 |
| 課題4 | 創エネ・エネルギー貯蔵・省エネルギー分野における革新素材・技術に関する研究 |
| 課題5 | 超スマート社会を支えるエレクトロニクス材料に関する研究 |
| 課題6 | マイクロナノシステム用途拡大につながる新規な材料・加工技術、及びデバイスに関する研究 |
| 課題7 | 生体機能を利用した新規合成・生産・製造に貢献する基盤技術と評価技術に関する研究 |
| 課題8 | 生体機能・生体分子に着目した革新的ライフサイエンス材料に関する研究 |
| 課題9 | 人に寄り添う新しい社会へ対応するための脳科学および感性科学の研究 |
| 課題10 | 持続可能な開発目標に資する材料設計・プロセス設計のための計算科学・計算工学・データ科学の研究 |
| 課題11 | 国内産業の強化・新産業創出に資する「新素材」実現のための基盤的研究 |
| 課題12 | サステイナブルな社会の実現に向けた革新的反応技術に関する研究 |
応募資格
- 国内の大学、またはこれに準ずる研究機関(大学共同利用機関、高等専門学校、公的研究機関)において研究活動に従事する人。(研究場所は日本国内に限ります)
- 2022年4月1日時点で満40歳未満の人。
- 受賞後少なくとも1年間は応募テーマを研究できる人。(ポストドクター、研究員は応募可能ですが、学部および大学院の学生は応募できません)
募集期間
2022年12月9日(金) ~ 2023年2月6日(月) 17時まで
選考件数
各研究課題につき原則として1件
助成金
受賞者には、助成金として1件につき100万円を個人に対して贈呈します。
研究目的であれば使途は限定しません。
応募方法
ご応募は下記ボタンをクリックして、必要事項をご記入の上、応募申請書を添付してお申し込みください。
以下の入力フォームは、12月9日(金)より有効になります。
問い合わせ先
公益社団法人新化学技術推進協会 新化学技術研究奨励賞・ステップアップ賞担当
〒102-0075 東京都千代田区三番町2 三番町KSビル 2F
TEL 03-6272-6880 FAX 03-5211-5920
E-mail jaciaward12@jaci.or.jp
新化学技術研究奨励賞ステップアップ賞は、研究奨励賞受賞後の研究に対して、切れ目の無い継続的な研究助成を行うことにより、研究成果の産業界への早期活用を図ることを目的に設けられたものです。
本年度の募集を12月9日から開始しますので奮ってご応募ください。
応募資格
- 研究奨励賞受賞後1年経過後から6年以内の方で、研究奨励賞受賞テーマを発展させたテーマ、またはその関連テーマについての応募であること。
- 国内の大学またはこれに準ずる研究機関(大学共同利用機関、高等専門学校、公的研究機関)において研究活動に従事して、日本国内で研究を実施すること。
なお、今回応募資格を有するのは、第6回(2017年度受賞)~第10回(2021年度受賞)の研究奨励賞受賞者の方々です。その方々にはメールで募集要項と応募書類をお送りします。
募集期間
2022年12月9日(金)~2023年2月6日(月)17時まで
選考件数
原則として1件/年以内とします。
助成金
受賞者には、研究助成金として、申請書に記載の予算額(上限300万円)を個人に対して贈呈します。研究目的であれば、使途は限定しません。
問い合わせ先
公益社団法人新化学技術推進協会 新化学技術研究奨励賞・ステップアップ賞担当
〒102-0075 東京都千代田区三番町2 三番町KSビル 2F
TEL 03-6272-6880 FAX 03-5211-5920
E-mail jaciaward12@jaci.or.jp
第12回新化学技術研究奨励賞 および 2023新化学技術研究奨励賞ステップアップ賞
第12回新化学技術研究奨励賞および2023新化学技術研究奨励賞ステップアップ賞の受賞者は、厳正なる審査の結果、以下のように決定しました。
受賞者の皆様、おめでとうございます。
また、多数のご応募を頂き、ありがとうございました。
◇ 2023新化学技術研究奨励賞ステップアップ賞
九州大学 大学院工学研究院 白木 智丈
『低次元ナノ材料への分子修飾に基づく新素材物質群の創出』
◇ 第12回新化学技術研究奨励賞
特別課題:
革新的化学工学に関する基盤的研究
名古屋工業大学 大学院工学研究科 古川 陽輝
『複数の液体混合を可能とする新たな邪魔板開発のための撹拌槽内未混合領域の解明』
課題1:
グリーンイノベーションを推進するための資源・プロセス・評価技術等に関する環境技術の研究
岐阜大学 工学部機械工学科 朝原 誠
『デトネーション加熱による高温メタン熱分解システムの検討』
課題2:
新しい資源代替材料・技術の創製、および資源の節約・回収・再利用に関する基盤的研究
名古屋工業大学 大学院工学研究科 成田 麻未
『アルミニウムのリサイクル過程における不純物除去技術の開発』
課題3:
バイオマス由来製品の事業化課題を解決する革新的な機能を有する素材の開発研究、又は革新的なバイオマス変換技術の研究
北陸先端科学技術大学院大学 サスティナブルイノベーション研究領域 高田 健司
『バイオアラミドの水溶化/水不溶化を利用したバイオコンポジット材料の創成』
課題4:
創エネ・エネルギー貯蔵・省エネルギー分野における革新素材・技術に関する研究
京都大学 化学研究所 中村 智也
『材料化学アプローチによる高性能ペロブスカイトタンデム太陽電池の開発』
課題5:
超スマート社会を支えるエレクトロニクス材料に関する研究
大阪大学 産業科学研究所 陳 伝彤
『次世代パワー半導体に向けたAg-ダイヤモンドの複合超高放熱エレクトロニクス実装材料の開発』
課題6:
マイクロナノシステム用途拡大につながる新規な材料・加工技術、及びデバイスに関する研究
早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 田中 大器
『ナノスケールで発現する特異的な化学反応解析デバイスの開発』
課題7:
生体機能を利用した新規合成・生産・製造に貢献する基盤技術と評価技術に関する研究
地球環境産業技術研究機構 バイオ研究グループ 清水 哲
『酸素非発生型光合成細菌による糖からの高効率バイオ水素生産技術の開発』
課題8:
生体機能・生体分子に着目した革新的ライフサイエンス材料に関する研究
東北大学 大学院工学研究科 浜田 省吾
『代謝するDNAハイドロゲルによるインテリジェント人工細胞外マトリックスの開発』
課題9:
人に寄り添う新しい社会へ対応するための脳科学および感性科学の研究
東京大学 大学院理学系研究科 香取 和生
『アルツハイマー病早期診断に最適化した嗅覚テストの開発』
課題10:
持続可能な開発目標に資する材料設計・プロセス設計のための計算科学・計算工学・データ科学の研究
中央大学 理工学部応用化学科 黒木 菜保子
『低副作用創薬を志向した生体イオン濃度下の第一原理分子動力学計算』
課題11:
国内産業の強化・新産業創出に資する「新素材」実現のための基盤的研究
名古屋大学 大学院工学研究科 平井 大悟郎
『安定・安全な酸化物トポロジカル材料の開発』
課題12:
サステイナブルな社会の実現に向けた革新的反応技術に関する研究
大阪大学 大学院工学研究科 岡 弘樹
『クリーンエネルギー製造に向けた有機高分子の革新的触媒能の開拓』
第12回新化学技術研究奨励賞および2023新化学技術研究奨励賞ステップアップ賞の審査委員は
以下の通りです。
(敬称略 所属、役職は、審査委員会時点のものです)
株式会社カネカ 常務執行役員 R&B本部長
上田 正博
東京農工大学大学院 工学研究院応用化学部門 教授
平野 雅文
大学共同利用機関法人自然科学研究機構 分子科学研究所 教授
江原 正博
大阪大学名誉教授 ・鹿児島大学名誉教授
明石 満
千葉大学 フロンティア医工学センター 教授
中川 誠司
国立研究開発法人産業技術総合研究所 総括研究主幹
秋永 広幸
東京理科大学 副学長 理工学部先端化学科 教授
井手本 康
東北大学大学院 工学研究科・工学部応用化学専攻 教授
冨重 圭一
DIC株式会社 執行役員 R&D統括本部長 総合研究所長
有賀 利郎
|