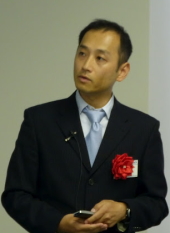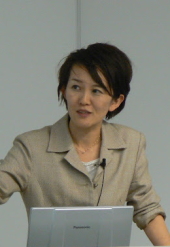各種募集
第1回新化学技術研究奨励賞
第1回新化学技術研究奨励賞の受賞者は、厳正なる審査の結果、以下のように決定しました。
受賞者の皆様、おめでとうございます。
また、多数のご応募を頂き、ありがとうございました。
課題1:特殊反応場を利用した高選択性触媒プロセスに関する研究
慶應義塾大学理工学部 河内 卓彌
『元素資源代替としての電気を利用した革新的触媒プロセスの開発』
課題2:世界に先駆ける新製品開発に資する「新素材」実現のための基礎的・基盤的研究
京都大学大学院理学研究科 山田 鉄兵
『細孔内物質の相転移コントロールによる「漏れない液体」』
課題3:省エネ・創エネ・蓄エネ材料の飛躍的な機能・性能向上を目指した計算科学的研究
東京工業大学像情報工学研究所 大野 玲
『オーダーパラメータに特徴付けられる乱れを考慮したバルクヘテロ有機薄膜太陽電池構造下でのエキシトン・電荷輸送シミュレーションの構築』
課題4:生体分子、またはその構造や生体機能からの着想・模倣、に基づく新規機能性材料の実用化を目指す研究
東京大学大学院工学系研究科 長田 健介
『DNA格納制御とPEG密度の定量的解析に基づく高分子ミセル型遺伝子キャリアの創出』
大阪大学大学院工学研究科 小野田 晃
『タンパク質階層プログラミングを基盤とするバイオデバイスの開発』
課題5:ゲノム工学を駆使した新規な物質生産プロセスの構築に関する研究
日本大学工学部 平野 展孝
『植物性バイオマス分解酵素複合体の合成生物学』
課題6:環境・エネルギー、医療・福祉および安全・安心生活空間など新たな分野におけるMEMS技術に関する研究
該当者無し
課題7:ユビキタス社会のためのデバイス用材料、システム、製造技術に関する研究
京都大学化学研究所 畠山 琢次
『有機薄膜太陽電池の高効率化を目指した含ヘテロ螺旋π共役分子の合成と集積制御』
名古屋大学大学院工学研究科 太田 裕道
『大きな熱電効果を示す極薄酸化物半導体の開発』
課題8:創電・エネルギー貯蔵分野における革新素材・技術に関する研究
大阪大学産業科学研究所 辛川 誠
『近赤外光利用有機薄膜太陽電池材料研究』
課題9:バイオマスを原料とする燃料・材料・化学品の高効率、低環境負荷製造技術に関する研究
独立行政法人産業技術総合研究所 山口 有朋
『セルロースから化学品を合成する低環境負荷型触媒反応システムの構築』
課題10:新しい資源代替材料・技術の創成に関する基礎研究
該当者無し
課題11:グリーン・イノベーションを押し進める実効的な資源循環・プロセス・評価技術に関する研究
豊橋技術科学大学エレクトロニクス先端融合研究所 吉田 奈央子
『導電性ナノ炭素材料を反応場とした微生物触媒による環境浄化およびエネルギー生産』
特別課題:東日本大震災からの復興に貢献する化学技術に関する研究
福島大学共生システム理工学類 高貝 慶隆
『放射性ストロンチウムの迅速分析手法の確立と東京電力福島第一原子力発電所事故に係わる広域土壌モニタリング』
東北大学金属材料研究所 黒澤 俊介
『小型・耐水放射線検出器による河川での放射線量モニタ用のシンチレーション結晶開発』
東北大学大学院環境科学研究科 畑山 正美
『津波堆積物由来重金属等への植物浄化法の適用』
第1回新化学技術研究奨励賞の審査委員は以下の通りです。
(敬称略 所属、役職は、審査委員会時点のものです)
受賞者の皆様、おめでとうございます。
また、多数のご応募を頂き、ありがとうございました。
課題1:特殊反応場を利用した高選択性触媒プロセスに関する研究
慶應義塾大学理工学部 河内 卓彌
『元素資源代替としての電気を利用した革新的触媒プロセスの開発』
課題2:世界に先駆ける新製品開発に資する「新素材」実現のための基礎的・基盤的研究
京都大学大学院理学研究科 山田 鉄兵
『細孔内物質の相転移コントロールによる「漏れない液体」』
課題3:省エネ・創エネ・蓄エネ材料の飛躍的な機能・性能向上を目指した計算科学的研究
東京工業大学像情報工学研究所 大野 玲
『オーダーパラメータに特徴付けられる乱れを考慮したバルクヘテロ有機薄膜太陽電池構造下でのエキシトン・電荷輸送シミュレーションの構築』
課題4:生体分子、またはその構造や生体機能からの着想・模倣、に基づく新規機能性材料の実用化を目指す研究
東京大学大学院工学系研究科 長田 健介
『DNA格納制御とPEG密度の定量的解析に基づく高分子ミセル型遺伝子キャリアの創出』
大阪大学大学院工学研究科 小野田 晃
『タンパク質階層プログラミングを基盤とするバイオデバイスの開発』
課題5:ゲノム工学を駆使した新規な物質生産プロセスの構築に関する研究
日本大学工学部 平野 展孝
『植物性バイオマス分解酵素複合体の合成生物学』
課題6:環境・エネルギー、医療・福祉および安全・安心生活空間など新たな分野におけるMEMS技術に関する研究
該当者無し
課題7:ユビキタス社会のためのデバイス用材料、システム、製造技術に関する研究
京都大学化学研究所 畠山 琢次
『有機薄膜太陽電池の高効率化を目指した含ヘテロ螺旋π共役分子の合成と集積制御』
名古屋大学大学院工学研究科 太田 裕道
『大きな熱電効果を示す極薄酸化物半導体の開発』
課題8:創電・エネルギー貯蔵分野における革新素材・技術に関する研究
大阪大学産業科学研究所 辛川 誠
『近赤外光利用有機薄膜太陽電池材料研究』
課題9:バイオマスを原料とする燃料・材料・化学品の高効率、低環境負荷製造技術に関する研究
独立行政法人産業技術総合研究所 山口 有朋
『セルロースから化学品を合成する低環境負荷型触媒反応システムの構築』
課題10:新しい資源代替材料・技術の創成に関する基礎研究
該当者無し
課題11:グリーン・イノベーションを押し進める実効的な資源循環・プロセス・評価技術に関する研究
豊橋技術科学大学エレクトロニクス先端融合研究所 吉田 奈央子
『導電性ナノ炭素材料を反応場とした微生物触媒による環境浄化およびエネルギー生産』
特別課題:東日本大震災からの復興に貢献する化学技術に関する研究
福島大学共生システム理工学類 高貝 慶隆
『放射性ストロンチウムの迅速分析手法の確立と東京電力福島第一原子力発電所事故に係わる広域土壌モニタリング』
東北大学金属材料研究所 黒澤 俊介
『小型・耐水放射線検出器による河川での放射線量モニタ用のシンチレーション結晶開発』
東北大学大学院環境科学研究科 畑山 正美
『津波堆積物由来重金属等への植物浄化法の適用』
第1回新化学技術研究奨励賞の審査委員は以下の通りです。
(敬称略 所属、役職は、審査委員会時点のものです)
| 東ソー株式会社 取締役 | 西澤 恵一郎 |
| 北九州産業学術推進機構 理事長 | 国武 豊喜 |
| 自然科学研究機構分子科学研究所 所長 | 大峯 巖 |
| 中部大学 教授 | 山根 恒夫 |
| 物質・材料研究機構 理事 | 曽根 純一 |
| 大阪大学 名誉教授 | 柳田 祥三 |
| 産業技術総合研究所 環境管理技術部門 部門長 | 田尾 博明 |
| 株式会社カネカ 執行役員 | 角倉 護 |
【平成22年度研究奨励金受賞研究の紹介】
|