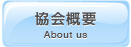The Advanced Chemistry/Materials Technology Subcommittee
先端化学・材料技術部会は、先端領域の化学技術革新への挑戦を主題として、反応開発、
素材開発、および計算科学技術の3つの分野に分け、
・高選択性反応分科会:化学反応・触媒反応プロセスの重要研究課題
・新素材分科会:諸産業を支え、社会課題の解決・持続可能な発展に資する「新素材」
・コンピュータケミストリ分科会:コンピュータケミストリ、情報科学分野の技術動向
を各分科会のテーマとして掲げながら、産・学・官の交流ならびに連携活動を行っています。さらに、化学産業の共通基盤となる技術を深めつつ、新しい技術動向についても調査・探索を行っています。また技術の融合をすすめ国際競争力のあるテーマを推進できるように、以下の3分科会の間での連携や、他の技術部会との交流も進めていきます。
また、各分科会では、毎年研究奨励賞の課題設定と一次審査を行い、大学・公的研究機関に所属する若手研究者の支援と育成に取り組んでいます。当部会活動に関わることで、産学官の人的交流が広がり、また自己研鑽にも役立つ場となっていますので、化学系企業の方々のみならず幅広い業種の方々、とりわけ若手研究者・技術者の方々の積極的なご参加を期待しています。
今後、より一層、多くの方々が当部会に参画していただくことを期待しています。
高選択性反応分科会
化学反応に関する重要研究課題や、革新的触媒反応技術や先端材料への応用技術などを調査し、研究支援して行くことにより、参加企業の新技術・新製品創出の一助となることを期待するとともに、日本の化学産業の競争力強化につなげるとの方針に基づいて活動しています。具体的には、環境負荷低減(二酸化炭素の排出量の削減、二酸化炭素の回収・利用、再資源化、低環境負荷原料の使用、廃棄物排出量の削減、有害物質の排出量削減、省エネルギー、省資源など)を重要な課題としながら、新技術によって生み出されたナノマテリアル等の新材料や、特殊な反応場、反応技術、データサイエンス、量子技術、新しい分析・解析技術等が、触媒反応の分野に対してどのような可能性(新しい触媒への利用、高機能・高性能化、工業的実用化など)を秘めているかを中心に調査活動を行っています。今年度も引き続き、革新的触媒反応技術やそれを応用した機能性材料への展開等に関し、基礎研究レベルから実用化検討レベルまで広く調査を行い、この分野の先端研究者による講演会の企画、関係機関等への訪問を積極的に行う予定です。また化学工学プロセスに関する若手研究員向け講習会として、基礎知識から実務的な内容の技術セミナーなども予定しています。
実際の企画や活動内容については、参加メンバーの意見や要望をできるだけ反映させることを心がけており、参加される方のメリットは大きいと考えています。
<具体的な活動内容、計画>
・分科会の会合を年6~7回、JACI事務所での対面形式の会議とweb会議の併用にて開催し、注目する研究者の講演会、後述の現地分科会、技術セミナー等を企画します。講演会は原則、分科会と同日、開催します。
・年1回、企業、大学、公的研究機関等を訪問する現地分科会を開催します。2023年度は、新素材分科会との共催で広島県の大崎クールジェン、CR実証拠点を訪問しました。
・化学工学の基本的な知識の修得を目的とした技術セミナーを毎年7月頃に開催します。
新素材分科会
近年、ナノ材料を筆頭に新たな機能を発現する素材・複合材が開発・提案され、その適用範囲はモビリティ、航空宇宙、エレクトロニクス、ロボティクス、医療、バイオ、情報通信、エネルギー、環境分野と多岐にわたっています。新素材分科会では、新規材料の発明発見にとどまらず、世の中で求められる社会的・経済的な価値の提供、即ちマテリアルソリューションに繋がるマテリアルインベンションに焦点を当てていくこととし、①従来にない新しい機能を発現する材料 ②従来の延長線上を大きく超えた機能発現レベルの材料 ③既存材料の機能を代替できる環境に優しく汎用・安価な材料などの観点で、インパクトのある話題や研究成果に焦点を当て、自由な議論の機会を提供していきます。新素材の適用領域は多岐にわたり、エネルギー問題、資源問題、環境問題等の社会課題の解決や社会の持続可能な発展に資することが期待されます。本分科会では、分科会メンバーによる議論を通して、ナノ構造材料、電子材料、次世代エネルギー関連材料、環境調和・CO2削減材料などのいくつかのテーマに基づいて活動を行うとともに、想定材料の出口に応じて、適宜他の分科会との共同開催や、その効果の共有化を図りながら進めていく予定です。
<具体的な活動内容、計画>
・分科会の会合を年6回程度、JACI事務所で開催しています。分科会メンバーで議論し、注目する研究者の講演会、後述の現地分科会、技術セミナーなどを企画しています。
・年1回、企業、大学、公的研究機関等を訪問する現地分科会を開催しています。2023年度は、高選択性反応分科会との共同開催で大崎クールジェン及びカーボンリサイクル実証研究拠点を訪問しました。
・新素材の基礎的な技術について講義をする技術セミナーを年1回程度開催しています。
・新素材関連の外部委託調査として、2021年度に「高分子材料分野におけるマテリアルズ・インフォマティクスの適用事例」について、報告書をとりまとめました。
コンピュータケミストリ分科会(CC分科会)
当分科会は、1989年に新化学発展協会が設立された当時に当該協会の部会活動の一環として発足して以来、計算化学、情報科学を企業の研究開発で役立てることを目的とした活動を継続しています。現在は、分科会全体の運営を担う「CC幹事会」と、各企業担当者の技術水準向上のための活動を行う3つのワーキンググループ(「高分子WG」、「次世代CCWG」、「情報科学WG」)で構成されています。各ワーキンググループでは、当該分野の第一人者である先生方に顧問となっていただき、基礎理論の習得や具体的なモデル課題に対する計算/解析の実習を行っています。これまでには、活動成果を学会発表したり、書籍として出版したりした実績もあります。さらに他の分科会等との技術横断的な協業も含めて、広く解決策を模索していきたいと考えています。
CC幹事会
CC幹事会では、主に会員企業で計算科学や情報科学の研究を担っているメンバーにより、隔月で会合を開催しCC分科会全体の運営を議論しています。コロナ禍によりオンラインの会合が続きましたが、2023年度からは協会会議室でオンサイトとオンラインを併用したハイブリッドでの会合を行っています。<具体的な活動内容、計画>
・CC分科会で実施している3つのWGの活動状況をモニタリングし、運営上の課題や方針について議論しています。
・新化学技術研究奨励賞の課題提案と応募案件の一次審査を当幹事会で実施しています。
・注目分野に関する勉強会を幹事会の開催に併せて実施しています。2023年度は、過去に新化学技術研究奨励賞を受賞された先生方をお招きして、最近の研究を紹介いただきました。今年度も継続する計画です。
・先端技術動向の把握を目的として、外部委託調査を行っています。2023年度には外部委託調査「欧米の化学系シミュレーションの最新動向」を実施しました。2024年度は「化学産業における生成AIの活用」の調査を計画しています
高分子WG
高分子シミュレーション技術セミナーを企画、運営し「ソフトマテリアル統合シミュレータOCTA」の活用研究を深めていきます。 また最新の研究動向や、高分子物性全般に関する実現象の理解を高めるために講演会も開催します。<具体的な活動内容、計画>
・月1回技術セミナーを、基本的にオンライン会議またはJACI事務所で開催し、個人やグループで取り組んでいる問題に対して議論を行います。
・年数回、関連する研究者の講演会を企画し、開催します。
・初学者を対象として、OCTAの基本的な操作方法や、基礎理論の勉強会も行います。
次世代CCWG
次世代計算化学技術セミナーを企画、運営し、量子化学計算および第一原理計算の活用研究を深めていきます。背景理論の勉強に加えて、企業や大学での研究事例やソフトウェア活用のノウハウを共有化し、参加者の計算化学技術を向上させます。さらに、次世代技術・最先端技術の理解を深めるために、産学官の研究者による講演会を開催します。<具体的な活動内容、計画>
・月1回技術セミナーを、JACI事務所およびWeb上でのハイブリッド形式で開催します。個人やグループで取り組んでいる課題に対して参加者間で議論し、また、顧問の先生方からアドバイスを頂き、課題解決を図ります。さらに、顧問の先生方による量子化学計算、第一原理計算の基礎講座を行い、背景理論からソフトウェアの使用方法まで講習します。
・年数回、量子化学計算や第一原理計算の基礎研究、応用研究で活躍する研究者による講演会を開催します。
情報科学WG
情報科学技術セミナーを企画、運営し、ケモ・データサイエンス(各種統計解析と機械学習)、マテリアルインフォマティックス(MI)分野を中心にデータサイエンス、プロセス、計測、事業企画への応用展開、あるいは生成AI活用、DX、IoT、AI全般の世の中の動向の活用研究を深めていきます。さらに、情報科学の理解を深めるために、産学官の研究者による講演会を開催します。<具体的な活動内容、計画>
・月1回技術セミナーを、JACI事務所で開催し、個人やグループで取り組んでいる問題に対して議論を行い、顧問の先生からの講義・ご指導を受けながら問題を解決します。
・年数回、情報科学に関する検討をされている研究者の講演会を企画し、開催します。
・化学×デジタル人材育成コミュニティサイトを運営するとともに、委託調査の活用や外部データベースの評価等を推進していきます。