| 盛況のうちに終了いたしました。 ご参加、ご協力いただきました皆様に御礼申し上げます。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 第10回 JACI/GSCシンポジウム ダイナミック・ケイパビリティ 変化する社会へ – 新化学の挑戦 – |
|||||||||||||||||||||||||||
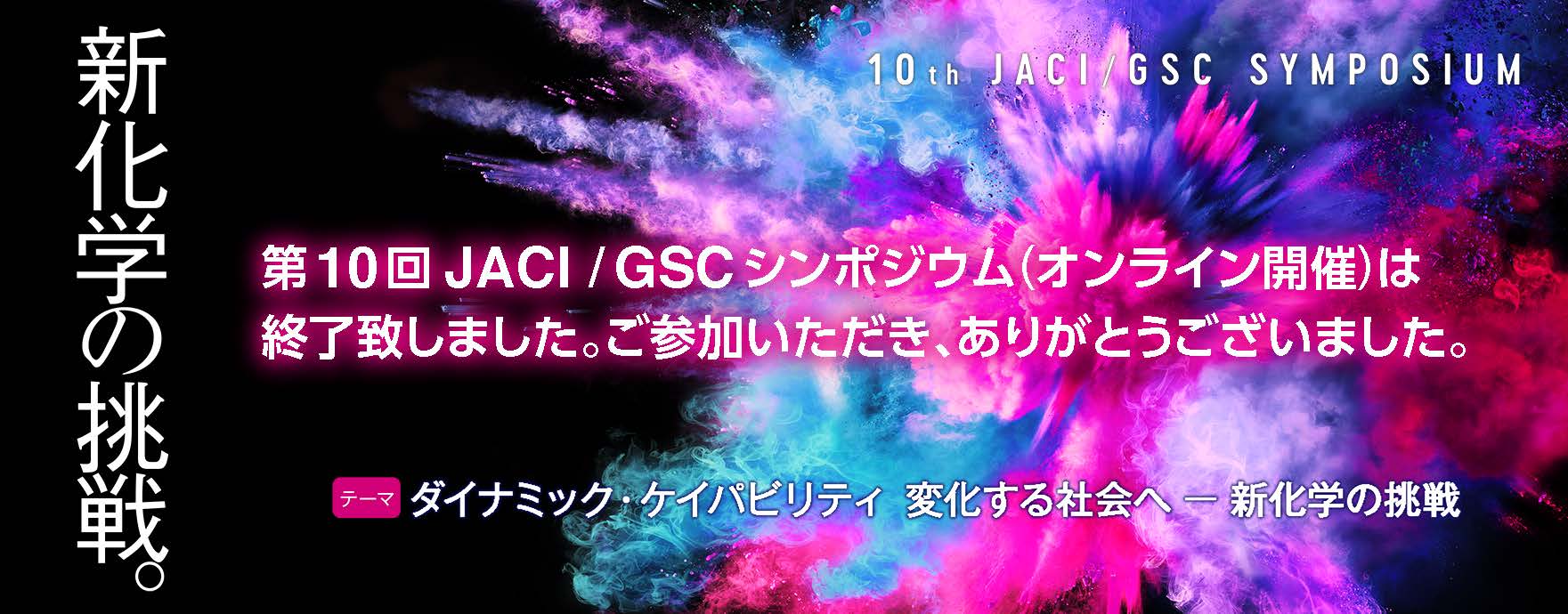 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
開催趣意書 公益社団法人新化学技術推進協会は、持続可能な発展のための化学技術イノベーションの推進を目的として、JACI/GSCシンポジウムを毎年開催しています。第9回シンポジウムでは、『新化学-未来社会への価値創造-』をテーマに、新たな時代を先取りする化学が未来社会で活躍するための進むべき方向性について論じ、新たな価値を創造するきっかけとしました。 第7回GSC東京国際会議において採択された「東京宣言2015」は、Green Sustainable Chemistry(GSC)の担う役割を、長期的・全地球規模の課題解決を図ること、健康で豊かな社会を持続的に発展させること、化学に関わる科学と技術を基盤とするイノベーションがこれらの牽引役となることとし、世界に開いた協調と連携により推進していくことを謳いました。その後、国連において「持続可能な開発目標 Sustainable Development Goals(SDGs)」が採択されました。SDGsは各国で大きな広がりを見せ、最近では、持続可能な社会の実現に向けた取り組みが広く推進されています。 一方、世界中で猛威を振るう新型コロナウィルス感染症は、我々の普段の生活に大きなインパクトを与え、社会環境の変化を強いてきました。その結果、産業構造もパラダイムチェンジとも言うべき大きな変化に直面し、未来社会の不確実性はますます高まっています。 持続可能な社会の実現のため、化学ならびに関連産業にとって、このような不確実性を含む大きな変動に対応して自らを変革していく能力、すなわちダイナミック・ケイパビリティを高めることは必須の課題であると考えます。これを涵養するにあたり、イノベーションを支え、持続的な競争優位性を産み出し産業としての力を革新し続けることは、SDGsの達成やSociety 5.0の実現に向けても重要です。また、ダイナミック・ケイパビリティを発揮するうえで、デジタルトランスフォーメーションの推進は欠かすことができない取り組みであり、従来の化学業界からは異分野ともいえる多くの技術について有機的な融合を進めていく必要があります。さらに、グローバルな資源循環型社会実現の重要性・緊急性は高まっており、この領域においても化学の貢献が期待されています。 第10回目の本シンポジウムでは、化学分野を超え幅広い分野からの講演等を通じて、化学が不確実な未来を切り拓くための進むべき方向性を提示します。本シンポジウムが、変化する社会に向け新たなイノベーションを創り出す『新化学の挑戦』の機会となることを期待します。 |
|||||||||||||||||||||||||||
日時2021年6月28日(月)~6月29日(火) |
|||||||||||||||||||||||||||
場所オンライン開催 |
|||||||||||||||||||||||||||
プログラム(敬称略)
1日目(2021年6月28日)
開会挨拶十倉 雅和 (公社)新化学技術推進協会 会長 基調講演 産総研の目指すオープンイノベーション 石村 和彦 (国研)産業技術総合研究所 理事長 産業技術総合研究所は、産業に関わる科学技術の研究開発により社会課題の解決を目指す、日本最大級の国立研究開発法人です。社会課題解決と産業競争力強化の共通解となるオープンイノベーションの重要性と、その推進のため産総研が実施する、特にグリーン・サステイナブルケミストリーに関する研究をご紹介します。 基調講演 地球と共存する化学 小林 喜光 (公社)日本化学会 会長/㈱三菱ケミカルホールディングス取締役会長 グリーン・リカバリーに向けた動きが加速する中で、Pollution SourceからSolution Providerへと生まれ変わった「化学」が地球規模の課題の解決に向けてどのような貢献ができるのか、当社の実践や日本化学会が果たすべき役割も含めて考えたい。 特別講演 マテリアル革新力強化による経済発展と社会的課題解決の両立 澤田 道隆 マテリアル戦略有識者会議 座長/花王㈱ 取締役会長 マテリアルは、社会・経済発展だけでなく、地球環境問題等の社会的課題解決のために、その重要性が増している。日本の強みであるマテリアル基盤力を生かし、それをイノベーション創出につなげる「マテリアル革新力」強化により、世界の先頭に立つべきと考える。 基調講演 サステナブルな社会の実現に向けた取り組みと自社の変革について 時田 隆仁 富士通㈱ 代表取締役社長 富士通は、自社のパーパス「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」に沿って、事業を通じた社会課題の解決に取り組んでいます。パーパスドリブンとデータドリブンの両輪で駆動する企業となるための取り組みについてご紹介します。 招待講演 メカノケミカル有機合成の登場と展開 伊藤 肇 北海道大学 教授 有機合成は基本的に有機溶媒中で行うが、最近、ボールミルを反応容器として、有機溶媒をほとんど使わずに効率よく有機合成を実施する方法が登場している。本講演では我々の研究グループの成果を中心に発表する。 GSCNビデオメッセージ Dr. Mary Kirchhoff, PHD <Director of Education, American Chemical Society Director, ACS Green Chemistry Institute> Prof. Buxing Han <Standing Committee Secretary, Interdivisional Committee on Green Chemistry for Sustainable Development (ICGCSD) IUPAC(International Union of pure and applied chemistry)> 御園生 誠 <東京大学 名誉教授> GSC賞受賞講演・表彰式 受賞者一覧はこちら(第20回GSC賞 )
2日目(2021年6月29日)
招待講演水電解が拓く水素エネルギー社会 光島 重徳 横浜国立大学 教授 CO2排出実質ゼロを目指し、再エネ電力のインバランスを解消して様々な部門で利用するために水電解水素製造が注目されている。本講演では、大規模システムに用いられるアルカリ水電解を中心に、変動電源での劣化とその対応について述べる。 招待講演 ナノからサブナノへ:原子ハイブリッド化学の展開 山元 公寿 東京工業大学 教授 ナノとサブナノの物質の世界は全く別物である。1ナノメートル前後のサブナノサイズの物質群は、ポストナノ材料として期待されているが、未だ未開拓のフロンティアである。原子の組み合わせを自在に操る「新化学」への挑戦を紹介したい。 招待講演 多孔体合成と応用展開 黒田 一幸 早稲田大学 名誉教授 ナノ空間を含む物質(多孔体)が盛んに研究され多方面に展開されている。種々の機能発現に空間が主要な役割を演じ、組成、構造、形態を制御した新物質開発が進んでいる。本講演では多孔体合成の進歩と空間の機能について数例を紹介する。 基調講演 ポストコロナとイノベーション 伊藤元重 東京大学 名誉教授/学習院大学 教授 コロナ危機からの経済の回復のプロセスでキーワードとなるのが、グリーンとデジタルである。これは経済のサプライサイドを強化するという意味で重要だが、この動きが企業の経営環境にどのような影響を及ぼすのか考えたい。 基調講演 ダイナミック・ケイパビリティ・ベースの日本企業に向けて 菊澤 研宗 慶應義塾大学 教授 不確実性が高まる中、今日、ダイナミック・ケイパビリティ論が注目されているが、そもそもダイナミック・ケイパビリティとは何か、そしてダイナミック・ケイパビリティを高めるために日本の企業・製造業はどうすべきか、などについてお話する。 ポスター発表 ポスター発表一覧はこちら 閉会挨拶 淡輪 敏 (公社)新化学技術推進協会 副会長 |
|||||||||||||||||||||||||||
参加費(税込)
|
|||||||||||||||||||||||||||
後援 (順不同) |
|||||||||||||||||||||||||||
|









